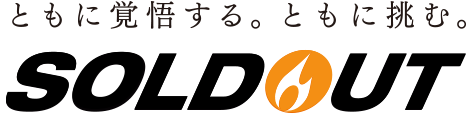──生成AI開発分科会の目的と役割を教えてください。
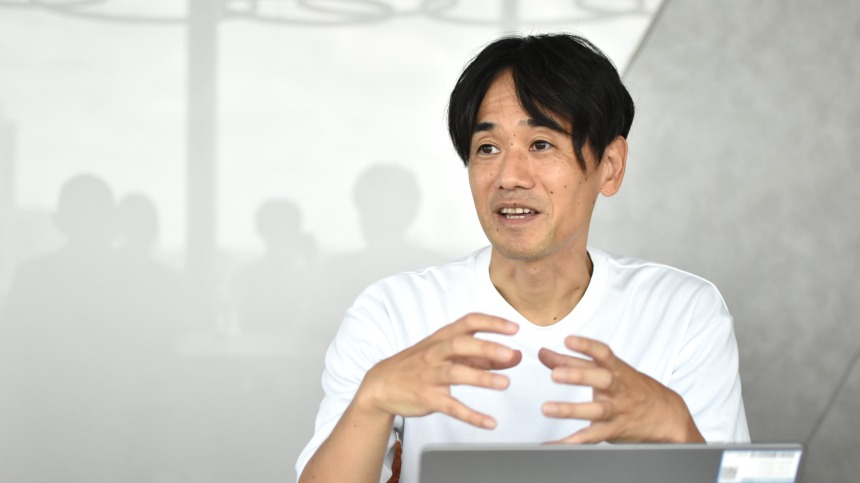
岡村:テクノロジー領域の情報連携が基本の役割です。あと、経営層が寄せる生成AIへの無尽蔵な期待(笑)と、エンジニアたちが実際にできること、やりたいこととのギャップをすり合わせてフィットさせることも個人的な目標としています。
──これまでの活動内容をご紹介ください。
岡村:2022年の末にChatGPT3.5が出たときから、社内でいろいろな人に触ってもらい始め、2023年夏ぐらいに組み込みツールを作り始めました。2023年初夏には博報堂DYグループ全体の生成AIの寄り合い横断グループ(現在の博報堂DYグループ Human Centered AI Institute)のようなものができていまして、ソウルドアウトグループ各社のCTOや開発責任者が参加しており、今も取り組みを続けています。
開発分科会のメンバーは、同じく各社のCTOや開発責任者の4名と、コーポレートの1名を加えた5名です。当初は各社が指定したメンバーでスタートしたのですが、博報堂DYグループの取り組みと重複する部分が出てきたので、最終的に同じ座組に落ち着きました。
──現状の成果と今後の展開についてお聞かせください。

岡村:成果は情報と体制の整理ができたことですね。プロジェクトが立ち上がって起きたことが2つあると思っていまして、1つは経営者層が考えていた「グループ全体でやろう、ツールを集約しよう」という流れから、各社で最適なものを使っていこうという流れになったこと。菊地さんの話にもあったように、会社によって最適なものが違うので、集約してしまうと不都合が起こるところが出てきてしまうため、無理に集約すべきではないと整理しました。
もう1つは、開発に関する認識ギャップの是正です。例えばSlackとOpenAI API(ChatGPT等)の連携は、知らない人から見るとプロダクト開発だと思われがちなのですが、エンジニアからするとExcelにマクロを入れるぐらいの感覚でできるものと、認識にズレがあるんですよね。数十分、数時間の作業だからやらせてほしいというエンジニア側の捉え方と経営者側のギャップも埋められたのではないかと思っています。
今後は、あらためて各社のCTOや開発責任者同士で現状を話す場ができたため、情報連携をして自社で開発しているものを発表する動きを取っていきたいと思っています。KPIとしてツール数を置いてはいるんですが、売れないものを作るばかりではしょうがないので、ただ数を達成するのではなく、使われるものを作りたいです。